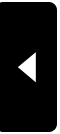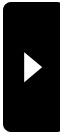2024年10月22日
いもほり(1・3・5班)



気持ちのよい天気の中で、さつまいもの収穫をしました。今年の夏はとても暑かったですが、さて、どんないもがどれだけ取れたでしょうか?昨年と比べると小ぶりで、焼き芋に適したサイズに思います。みんなとお家の方の分を合わせた数が収穫できることを期待します。明日は、2・4・6班が行います。
2024年10月21日
読み聞かせ


今週も、読み聞かせがありました。低学年は、「さつまのおいも」という今の季節にぴったりの絵本でした。中学年は、「天の火をぬすんだウサギ」という絵本でした。赤羽末吉さんの絵がお話の雰囲気にぴったりで、子どもたちは、集中して聞いていました。毎週月曜日のこの時間を子どもたちは楽しみにしています。
2024年10月21日
あさがおの種とり



10月の初めごろまで、花を咲かせていた「あさがお」ですが、さすがに、ツルも葉っぱもカリカリになってきました。2年生が、「ふくらみが大きいのを選ぶと、中から大きい種が出てくるよ。」と教えてくれました。天気が良くて乾燥しているので、種も取りやすいです。
2024年10月18日
2024年10月17日
2024年10月17日
2024年10月16日
生活科で秋の材料を使ったおもちゃ作り




どんぐりとまつぼっくりを使って、おもちゃができないか考えました。すぐに思いついたのは、どんぐりごま。ペットボトルにどんぐりを入れて、マラカス。どんぐりを転がすどんぐりめいろ。作っては、自分たちで試して、改良して。どんどんレベルが上がっています。おもちゃコーナーができたら、2年生を招待しようかな。相談中です。
2024年10月15日
足踏み脱穀機に挑戦
秋晴れの日の午後、5年生は千枚田でとれた米を脱穀しました。

学校に保管されている足踏み脱穀機を使いました。
道具を前にさっそくよい気付きをした子どもたち。横書きの文字は右から読むと意味が通じます。
「これってだいぶ前のものだよね。」「最新式って書いてあるけど、どれくらい前のかな」
そんな声が聞こえてきました。コンバインで稲刈りしてしまえば、あっと言う間にすむ作業ですが、
体験を通して、昔ながらの米作りの作業を学びます。
脱穀機のあとは、唐箕です。レバーを回すと、きれいに米の形状になりました。

今年は、鹿の被害にあい、収穫が昨年より少なかったようですが、
保存会の小山さんや運転手さんたちの協力のおかげで、無事、米ができました。
学校に保管されている足踏み脱穀機を使いました。
道具を前にさっそくよい気付きをした子どもたち。横書きの文字は右から読むと意味が通じます。
「これってだいぶ前のものだよね。」「最新式って書いてあるけど、どれくらい前のかな」
そんな声が聞こえてきました。コンバインで稲刈りしてしまえば、あっと言う間にすむ作業ですが、
体験を通して、昔ながらの米作りの作業を学びます。
脱穀機のあとは、唐箕です。レバーを回すと、きれいに米の形状になりました。
今年は、鹿の被害にあい、収穫が昨年より少なかったようですが、
保存会の小山さんや運転手さんたちの協力のおかげで、無事、米ができました。
2024年10月11日
玖老勢郵便局にてアイデア貯金箱の展示


夏休みに取り組んだアイデア貯金箱。低学年は必須課題でした。その他の学年でも自主的に取り組んだ人もいて、アイデア抜群、ユーモアのある作品が揃いました。玖老勢郵便局で、今月25日ごろまで、展示予定です。どうぞ、ご覧ください。
2024年10月11日
秋を感じながら、校外学習




1年生だけで行く2回目の校外学習でした。目的は、折り紙ごまをいただいたしげ子さんにお礼をすること。鳳来寺山自然科学博物館で催されている「どんぐり展」を見学することです。事前指導で、挨拶のこと、マナーのことを確認したので、1年生なりに気をつけて、行動していました。学校に戻って、感想を聞いたら、みんな口をそろえて、「楽しかった!」と言っていました。